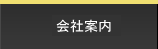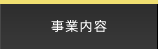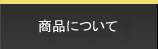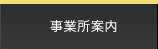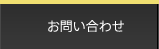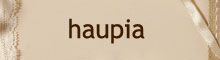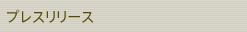
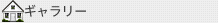
オリジナル・テキスタイル商品を自由にゆっくりご覧頂けます。
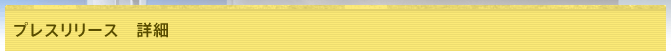
甦れ ファッションビジネス 第1部 改革の条件 下請けからの転換 〜〝自ら動く〟服地卸へ〜 “繊研新聞 平成21年11月11日(水)”
「東京の大手アパレルからワンコイン(500円)のプリントを要求された」と嘆くのは京都の中堅服地卸。中国を始め、アジア各国での素材現地調達が加速する中、生き残りをかけた国内服地卸への厳しい要請が次々とぶつけられてくる。
大阪の中堅服地卸のトップは「今のままでは残っていけない」と言い切る。バブル崩壊後、服地卸に追い風が吹いたことはない。じり貧傾向の売り上げをぎりぎりの利益でしのいできた。厳しい価格に加え、ロットの細かさが目立つ。5反、10反のまとまった取引は珍しく、1反にも満たぬ半反、20㍍などという受注も入る。アパレルの企画はシーズン中に2度も3度も変わる。そして今年は、これまでより20〜30%を越えるコストダウンを余儀なくされている。「今年、来年で勝負が決まる」(大阪の大手服地卸)と言われるほど、もう一段の厳しい生き残りが迫られている。
バブル崩壊後、生産の海外移転、高級化路線の崩壊、アパレル、小売の素材調達の変化という大きな流れの中で、百貨店、専門店、量販店アパレルをフォローしてきた服地卸が衰退、とくにミセス向けのブランドを主力にしてきた京都の有力卸が軒並破綻した。ロンシャン、セルマー、市田テキスタイルの蹉跌に加え、この数年では京絨が破産、今年夏には美濃利が廃業した。残っている企業の多くも売り上げは最盛時の10分の1だ。
大手、中堅アパレルの展示会を待ち、受注状況に合わせて生産、数ヶ月後の現反納期に合わせるという方式は、バブルの追い風の中では有効に作用していた。しかしバブル崩壊後の変革の波は隠された問題を一気に噴出させた。アパレルの言いなりに作り、変更し、納め、素材が残れば引き取り、不良在庫として積まれる。
倒産した大手服地卸の元幹部は「結局はアパレルの下請けであり、どこにもイニシアチブがなかった」という。また廃業した企業の別の幹部は「消費者に接することなく、仮需の中での情報に翻弄された」。
生産の海外移転の増加につれてコスト意識は高まっていたにもかかわらず、海外を産地として見る対応も遅れた。現在残った多くの服地卸は新たな仕組みを構築するどころか在庫をもつゆとりもなくなりつつある。
一方でこうした流れをいち早く把握して服地卸の新しいビジネスモデルの構築に力を注いできたのはサンウェル。扱う素材のすべてに在庫リスクを張り、いつでも販売できる体制を整え、今や扱う素材は1200マークを超える。7年ほど前からはネットでの素材販売を開始、扱う素材のすべてを、1㍍でも即日発送するシステムだ。ネットでの売り上げは年間12億円を超える。服地卸としてはいち早く中国にも拠点を構え、海外で開発した素材も100マークを超える。同時に、中国及び近隣国への素材販売も「この数年で手応えが得られ始めた」。
また、宇仁繊維では得意の合繊薄地をベースに意匠素材も合わせて約1万品種を常時在庫、1反から即日販売する機能で創業10年にも満たないが、すでに年商 40億円近くにまで成長した。同社は北陸に自ら織機を抱え、染工場にも独自の生産ラインを確保、「メーカーとして、徹底してコストを追及する」姿勢を貫く。
婦人服地卸の規模縮小が続く中、一時はシェアを拡大し「一人勝ち」とも言われた瀧定大阪でさえ、半世紀にわたって有効に機能していた「課別独立採算制が行き詰ってきた」と瀧隆太社長は言う。今後3年間で大きな転換を図る。
9月末には初めて中期経営計画を発表した。10〜12年度に事業部制の導入、海外事業の拡大などを掲げた。事業部制は、来年2月からテキスタイル営業部隊で先行的に導入する。テイストや年代など市場別に3〜5の事業部を設ける予定だ。海外事業の拡大に向けては、今年11月に上海、07年秋にニューヨークで現地法人を設立した。香港事務所とも連携して、日・中・欧米間の三国間貿易や日本からの生地輸出の拡大、中国での生地調達機能の拡充を目指している。
今年はすべての服地卸がかつてない厳しさの中にある。このまま推移してさらに蹉跌を迎える服地卸や産地企業が増えれば、品質の高さ、感性を表現する技術が消える。とくにプリントを始め、染色の分野は深刻だ。「生地のコスト以前にアパレルは他にコストを下げる要因がある」というのは服地卸に共通した声だ。服地卸の苦悩は続くが、それはいずれ国内の苦悩にもつながる可能性も高い。